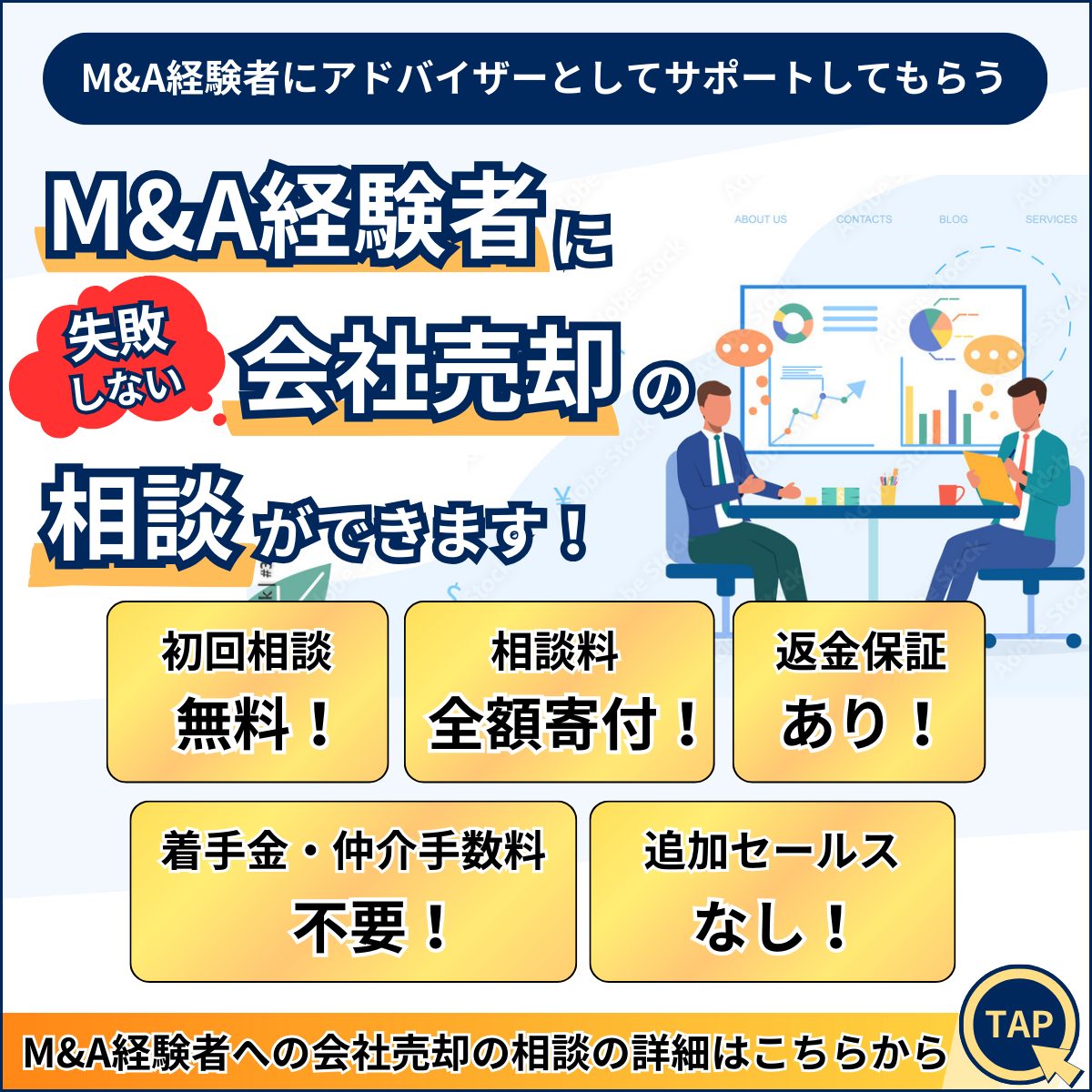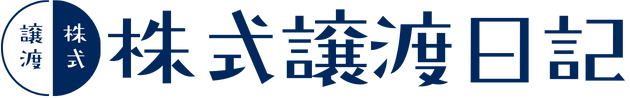「よし、これで自分がいなくなっても会社の売上は上がり続けるぞ」
会社売却に向けて、自分がいなくても会社がまわるよう事業の自動化を意識した僕は、M&A仲介会社さんに依頼する4ヶ月前に上記のように思うことができました。
買い手企業にとっては、事業内容やビジネスモデル、決算書や月次数字などを見て買収に魅力的な会社だと思っても、社長いないとまわらない仕組みになっている場合は、買収を躊躇してしまいます。
ということで今回は事業の自動化について書いていきます。

自分の属人的要素はトコトン排除
中小企業の経営の場合、「経費がもったいない」とか「自分がやった方が意思決定と実行が同時に進むから早く済む」とかの理由で、社長自らがタスクを処理することがけっこう多いのではないでしょうか?
実際に僕も同じ理由で、大口顧客の対応や、メディア対応、クレーム対応、部門会議の仕切りなどは自分がやっていました。いわゆる、プレイングマネージャーというやつだったと思います。
しかし、売却するためには、M&Aプロセスが始まる前(売却案件化する前)に、このような社長の属人的要素はトコトン排除する必要があります。
売却案件化前に「自分がいなくても会社はまわるか?」と自分に問う
売却案件化する前に、自分にこの質問をして、回答が「まわる」であればOKです。
回答が「まわらない」の場合は、「社員に引き継ぎできるか?」ということになります。
引き継ぎ対象については、M&Aプロセスの前なので、できれば自社内で「売却後も残る幹部に引き継ぐ」もしくは「社員を昇格させ、昇格後の業務として引き継ぐ」ことで、会社がまわる状態にして、売却案件化すると良いでしょう。
自分の場合は、
- 大口顧客・メディア対応は既存幹部に引き継ぐ。
- クレーム対応は中途採用で業務を覚えてきた社員に引き継ぐ。
- 部門会議の仕切りは既存社員を昇格させ引き継ぐ。
というように担当者を決めました。
それら担当者に対して、オペレーションルールを明確にしたうえで引き継ぎを行い、実際に実行させてみて、エラーが発生しなくなるまで付き合いました。
経営の自動化の完了
自分の業務を引き継いだ担当者が実行しているなかで、エラーが発生しなくなったら引き継ぎの完了です。
引き継ぎが完了した後、社長の自分から見て、「そのまま経営を継続していたら、自分がその業務をせずともチャリンチャリン入ってくる状態で、その状態が3年続いても確実に売上げが維持できると想定できれば、自動化も完了」といえます。
そうなれば、残る社長としての業務は「経営のみ」になります。この部分は買い手企業の新経営者に引き継ぎをしていくことになります。
M&Aプロセス中に、自分に対して「自分がいなくなっても会社はまわるか?」と問うた時、自信を持って「まわる!」といえる状態にしておきたいですね。